(2023.07.23.改訂)
単元制度とは?
日本の株式市場には「単元株制度」という仕組みがあります。
各銘柄毎に売買できる単位(単元)が決められていて、単元が100株であれば100株単位でしか売買する事ができません。
東京証券取引所の指導もあって単元は100株の銘柄が主流になりつつありますが、1,000株単元の銘柄もかなり存在します。
他にも1株、10株、50株単位などさまざまな単元が存在しているのが実状です。
買いたい銘柄の株価が1,000円だったとしても、単元が100株だったら1,000円✕100株=10万円(+手数料)の資金が必要になるわけです。
資金の豊富な方はただ購入すれば良いと思いますが、10万円を出すのは怖い・難しいと言う方も当然いらっしゃると思います。
最近では株価が100円前後の銘柄も数多くありますのでそうした銘柄であれば100株単元だと1万円前後とかなりお手頃にはなります。
ただ自分の欲しい銘柄の株価が高かったりあるいは単元が1,000株だったりすると、購入のハードルがグンと上がってしまいます。
でもどうせなら好きな銘柄の株を購入したいと思った時、良い方法は無いのでしょうか。
1株からでも買える
証券会社の中には単元未満株と言うものを扱っている会社があります。
ミニ株、S株、ワン株など名称は証券会社によって違いますが、単元数より少ない株数で売買できるサービスと言う事です。
単元未満株を扱っている多くの証券会社の場合は、単元株が100株だったら10株単位と言った具合に単元数の1/10の単位を1口として、個々の注文を証券会社が纏めて注文すると言うサービスである事が多いです。
但し証券会社の中には1株単位で株を売買できるサービスを展開している会社もいくつか存在します。
●SB証券(S株)
●マネックス証券 (ワン株)
●カブドットコム証券(プチ株)
上記3社では、1株単位から株を売買する事が可能です。
トヨタもJALも買いやすい
例えばトヨタ自動車(7203)の株が欲しいと言った場合、普通に買うと単元は100株なので20万円以上の資金が必要になりますが、SBI証券のS株であれば、2023年7月21日の終値で2288円(+手数料)で購入ができます。
かなり身近になってきたのでは無いでしょうか。 同様に
・日本航空(9201) 3,070円 (+手数料)
・三菱地所(8802) 1,715円(+手数料)
となります。
更にセブン銀行(8410)などになると288円 (+手数料)まで購入価格が下がってきます。
購入のハードルが驚くほど下がりますね。
注文は成行注文のみです
ここからはSBI証券が展開する単元未満株サービス「S株」を例に解説します。
S株では基本的に東証プライム、スタンダード、グロース市場(旧1部・2部・マザーズ・JASDAQ市場)に上場している銘柄の売買取引を1株単位で行なう事ができます。
S株では例えば営業日の午前10時に買い注文を入れると、証券会社側で10時半までの全ての注文が纏められて午後の取引市場(後場)の開始値で成行注文されます。
買値(売値)を指定する指値注文をする事はできません。
東証銘柄の注文と執行の時間は以下の通りです。
| 注文時間 | 執行のタイミング |
| 0:00~07:00 | 当日の前場始値での買付·売却 |
| 07:00~10:30 | 当日の後場始値での買付·売却 |
| 10:30〜13:30 | 当日の後場引けでの買付・売却 |
| 13:30~24:00 | 翌営業日の前場始値での買付·売却 |
手数料
SBI証券のS株取引の手数料は2023年7月時点で買い付け時の手数料が無料となっています。
最低手数料金額の設定も無いので単純に株価分の費用だけで買えてしまう事になります。
約定金額が10,000円迄は手数料は54円と言う事になります。
従って先程のトヨタ自動車の例でも手数料は0円です。
売却の時には約定金額の0.55%の手数料がかかります。
元々単元未満株のサービスは単元未満でも売買ができる変わりに手数料は割高に設定される事が多かったので買付時手数料無料というのは非常に魅力的です。
但しここで挙げた手数料額は全てインターネットで注文する場合の金額です。
電話でオペレーターに注文する場合は、いずれもこれより遥かに金額が高くなりますので御注意下さい。
14円上がれば利益がでる
前述のトヨタ自動車(2,288円)の場合、0.55%の手数料が売る時の2回掛かるので株価が14円以上上がると利益が出る事になります。
セブン銀行(288円)を1株だけ購入する時も3円以上上がれば利益がでる事になるのです。
ちゃんと株主です
単元未満の株を買った時、その名義はどうなるでしょうか。
実は単元未満株の場合も単元株同様に証券保管振替機構の名義となりますが、実質的には購入者が株主として扱われます。
1株でもれっきとした株主なのです。
株主への配当もちゃんと保有株数の分貰う事ができます。
NISAでも使える
S株はNISAロ座でも売買をする事ができます。
NISA口座では売買利益への税金(20.315%)が掛からないのでありがたですね。
但しつみたてNISAでの取引は対象外となっているのでそこは注意が必要です。
単元未満株を買い増しして単元株にすることもできます。
株式分割等で思わぬ形で単元未満株が発生するケースがあります。
そんな時もS株では単元株に足りない株数を買い増しして単元株にする事が可能です。
何段階かにタイミングを分けて購入して単元株にするなんて戦略も取れるのです。
単元未満株のデメリット
単元未満株のデメリットとしてはどの様なものが挙げられるでしょうか。
主な項目としては
●株主優待が受けられない
●株主総会に出られない
と言った項目が挙げられます。
株主優待が受けられない
株式投資で人気の株主優待ですが、通常は単元株以上の株を保有している人しか優待の対象になりません。
従って殆どの銘柄では株主優待を受けられない事になります。
以前は単元未満の株主にも株主優待特典を設定していた銘柄が結構あり、そうした銘柄に集中して投資する方法などもありました。
しかしながらそうした銘柄は年々縮小し、以前の様なお得感もありません。
株主総会に出られない
株主総会も殆どの会社では、単元株以上の保有を参加資格としています。
その為、単元未満株の保有では株主総会にでる事ができません。
まとめ
単位未満株制度は資金の潤沢で無い方にも株式投資の選択肢を拡げてくれるものです。
資金が潤沢で無くても、自分が好きな会社、応援したい会社の株式を買う事を可能にしてくれます。
ディズニーランドが好き、と言う理由でオリエンタルランドの株を買うと言う事が容易にできるのです。
分散投資にも非常に有効です。
上手に使って投資の幅も利益も拡大して下さい。
今日も最後までお読み頂き、 ありがとうございました。
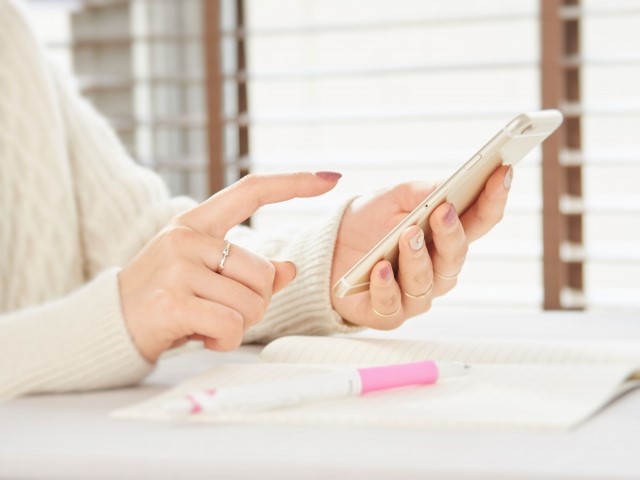


コメント